もう手放せない!! 日本画の筆との出会い。
まだ、水彩画を始めて間もない頃、なんとなくYouTubeで水彩画を描く動画を見ていて、「あれ?この人、水彩画を描いてるけど、日本画の筆を使ってる??」と、筆に目が釘付けになりました。
そのあと、日本画の筆が気になって、YouTubeで水彩画を描くチャンネルをあちこち見てみると、水彩画の作家さんが日本画の筆を使っている場面を頻繁に見かけました。
その繊細な動きの筆先から生まれるタッチがとても魅力的に見えて、「私もこの筆使ってみたい!」と思い立ち、初めて購入してみたのが「彩色筆」でした。
その後は、日本画の筆にすっかり魅了され、彩色筆だけなく、杖立筆や面相筆、削用筆など、様々な種類の日本画の筆を試していくようになり、私の主力の筆となっていきました。
日本画の筆は、水彩画を描く方にもきっと新しい発見と表現の幅を広げてくれるはずです。
この記事があなたの日本画の筆との素敵な出会いのきっかけになれば嬉しいです。
 ゆい
ゆい
私が実際に使ってみて感じた
日本画の筆の魅力
具体的な使い方
初心者でも扱いやすい筆の選び方
などを詳しくご紹介します。
水彩画の筆と日本画の筆の違いとは?
見た目の違い


●水彩画の筆
穂先の根元に「口金」と呼ばれる金具が付いていて、口金で穂の部分をギュッと押さえて穂先を軸に取り付けてあります。
●日本画の筆
軸の材質が主に竹で出来ており、水彩画の筆のような「口金」は付いておらず、竹の軸からそのまま穂先が付いています。
また、軸の竹の作りは寸胴で、水彩画の筆のように、太くなったり、細くなったりせずに、真っ直ぐなつくりになっています。
サイズ表記の違い


●水彩画の筆
「6号」「15号」など数字の号数表示で、サイズの種類が多く分かれています。
●日本画の筆
数字の号数表示がされている筆もありますが、「小」「中」「大」「別大」など、サイズが日本語表記されている筆が多いです。
穂先の材質の違い
日本画の筆は、主に獣毛でできていますが、水彩画の筆は、獣毛の特徴を再現した特殊なナイロン製のものも多く販売されています。
日本画の筆は水彩画にも相性ピッタリ!!





今ではすっかり私の主力の筆となってしまった日本画の筆を詳しく紹介していきますね。
水彩画でも大活躍!日本画の筆
ちょっとしたきっかけで使い始めた日本画の筆でしたが、山羊の毛で出来た彩色筆は、使ってみると水含みの良さが抜群でした。
また、穂先が柔らかいので、重ね塗りをしても下に塗っている絵の具を削り取ってしまうことがなく、きれいに色を重ねて塗ることができました。
穂先の柔らかさを活かして、絵の具をぼかすのに使ったり、筆の側面を使って、ドライブラシもできますし、穂先を割りボサボサ状態で草を描いたり、筆先を揃えて使うと、木の細い枝も描けます。
という具合に、1本の彩色筆で様々な描き方ができるのです。
「これは良い筆をみつけた!」と思いました。
初心者にお勧めの日本画の筆は?
私が使ってみた経験から、初心者の方が初めて使う日本画の筆として、次の2本をおすすめします。


●彩色筆
日本画の筆は、値段の高いものも多いのですが、「彩色筆」はお手頃価格で手に入りますし、彩色筆1本で様々な使い方、描き方ができます。
穂先が柔らかいので、普段張りのある筆を使い慣れている方には、少し慣れが必要かもしれませんが、慣れてしまえばきっと手放せない1本になると思います。
また、彩色筆には穂先の長いタイプの「長穂彩色筆」もあります。
こちらは、長い穂先を横にして塗ることで、「彩色筆」より広い面を塗ることができます。


●面相筆
細い線を描くのに適しています。
穂先の長さが1.5cmくらいのものを選ぶと描きやすいです。



まずはこの2本から試してみよう!
日本画の筆|代表的な筆の種類とその特徴・使い方
日本画用の筆は、大和時代に中国からやってきたと言われていますが、江戸時代末期から明治時代にかけて試行錯誤しながら作り上げられ、現在に至るようです。
このように、日本画の筆は歴史が古く、職人さんが長年かけて、その繊細かつ高度な技術の粋を極めて作られた一品なのです。
それを考えると、日本画の筆が「描きやすい」「描き心地がいい」と感じるのは、当たり前だとも言えますね!
ここでは、私が持っている日本画の筆を中心に、種類ごとにご紹介します。



素晴らしい職人技で作られた、日本画の筆を使わないのはもったいないよね!



日本画の筆は、毛先が柔らかいものが多いので、パレットに固めておいた絵の具は取りにくいことがあります。
絵を描く前には、パレットの絵の具にスプレーで水をかけておいて、絵の具を柔らかくしておくと使いやすいですよ。





スプレーボトルは
100円ショップにもあるよ!
彩色筆
毛の材質
羊毛がベース。馬・鹿・狸など
特徴・用途
羊毛をベースに作られているので、絵の具をたっぷり含み、主に着彩に使用されますが、着彩以外にも、様々な使い方ができます。毛先を割って、ボサボサにした状態で「草」の線を描いたり、穂先をキレイにまとめると細い線も描くことができます。毛が柔らかいので、下に描いた絵の具を削ることなく、重ね塗りや、色をぼかしたりなど、幅広い用途に使用できます。



穂先の長い「長穂彩色筆」もあります。
杖立て筆「長流」


(画像の「大」と「小」の筆はまだおろしていないので、穂先が糊で固められています。中央の筆はおろして使っている状態です。)
毛の材質
羊毛・馬・鹿・狸 など
特徴・用途
彩色筆より穂先が長く、適度なコシがあります。彩色筆と同じように、着彩から線描まで幅広い用途に使えます。穂先が長いので、広い面に着彩できます。



私は、「長流」を主力の筆として使っています。
平筆
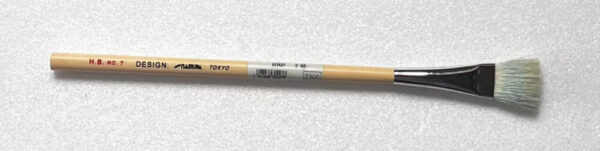
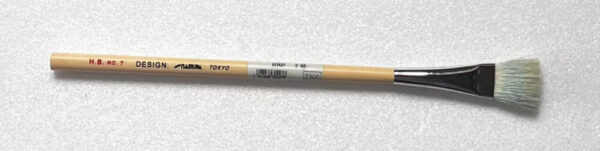
毛の材質
羊毛
特徴・用途
口金で毛を平らにまとめて作られています。羊毛なので絵の具の含みが良く、グラデーションなど、広い範囲の塗りや、ぼかしに使用するのに便利です。
削用筆


毛の材質
羊毛・イタチ・狸 など
特徴・用途
鋭角に尖っている穂先の形が特徴的な筆です。絵の具の含みが良いので、途中で絵の具の付け足し無しで細い線を長く引くことができます。コシがあるので、筆圧により、細い線から太い線まで自在に描くことができますし、筆の側面を使って広い面の彩色にも使えます。このオールマイティーに使える点で、削用筆は多くのアーティストに愛用者が多い筆でもあります。



私は、削用筆を使って、作品にサインを入れる際にも使用しています。
面相筆
毛の材質
イタチ・狸
特徴・用途
細い線や、細部の着彩などに使用します。用途により、材質や穂先の長さに様々な種類があります。動物の毛並みを描いたり、木の枝や電線を描いたりなど、細い線を描くのに便利です。
刷毛


毛の材質
羊毛
特徴・用途
広い面を一気に塗る時や、水彩紙を水張りする際にも使用します。大きなサイズの水彩紙に描く時には必須の筆です。背景の塗りや、空などの広い面を塗る時、また、グラデーションを描く時など、ムラなく絵の具を塗ることができます。ウエットインウエットの技法の際に、水を引くのにも便利に使えます。刷毛が乾いた状態で、ぼかしに使うこともできます。
隈取筆
毛の材質
羊毛・馬・鹿
特徴・用途
穂先が丸く水含みの良い筆で、水を付けた隈取筆で、絵の具をぼかすのに使用します。花びらなど、絵の具の濃淡を美しく描きたい時に使うと便利です。
連筆


毛の材質
羊毛
特徴・用途
筆を横に数本並べて束ねた形状の筆。絵の具の含みが非常に良く、広い面を塗るのに適しています。刷毛と比べて、筆を並べた作りになっているため、穂先が効いて、繊細な描写も可能です。



初めて連筆を見た時は、この斬新な形に驚いたよ!



連筆の本数はいろいろあるので、小さなサイズの作品が多い場合は、「3連筆」で試してみるといいかも。
日本画の筆|メーカー紹介
日本画の品質の良い筆を製作、販売されているメーカーは沢山あるのですが、その中でも私が使ったことのある、お気に入りの日本画の筆のメーカーを紹介してみます。
宮内不朽堂(みやうちふきゅうどう)
明治5年(1872年)創業の歴史ある筆の老舗です。
横山大観や、東山魁夷も不朽堂の筆を愛用していたそうです。


私の愛用の筆は画像の筆です。
その中でも「長穂彩色筆」を私の主力の筆のひとつとして使っています。
この筆は、毛先がなめらかで繊細に動いてくれるので、花などの植物を描く際に重宝しています。
また、削用筆を作品のサインを入れる時に使用しています。
削用筆は、穂の根元は太く、毛先が細く尖った形をしているので、絵の具の含みが良く、途中でかすれることなく細い線で作品にサインを書くことができて便利です。





歴史を感じる工房だね!
上の写真は宮内不朽堂の工房の入口ですが、歴史を感じるたたずまいですね!
私は、直接工房に伺ったことがあるのですが、引き戸を開けて中に入ると、数名の職人さんが筆を制作されている最中でした。
私の記事に工房の写真や、不朽堂さんのホームページのURLを紹介してもよいかどうかお尋ねしてみたところ、快く承諾していただきましたので、以下に載せておきます。
定期的にセールもされていますので、ホームページをのぞいてみてくださいね。
<宮内不朽堂 ホームページ>
https://2910fude.jugem.jp/
通信販売で購入することもできるそうです。
墨運堂(ぼくうんどう)
文化2年(1805年)創業の墨を製造されている老舗の会社ですが、日本画の筆も制作販売されています。
私は、「長流」の中サイズを基本の筆の1本として使っています。
見た目は不朽堂の長穂彩色筆と似たような筆に見えるのですが、こちらの方が少しコシがあるので、主に風景画を描くときに使用しています。
清晨堂(せいしんどう)
日本画の筆として代表的な「削用筆」「長流」などの筆を、明治時代に考案した「宮内得應」の技術を受け継いでいる筆の工房です。
清晨堂としての実店舗は無く、筆を購入する際は、オンライン又は画材店での購入となります。
名村大成堂(なむらたいせいどう)


昭和15年(1940年)創業、筆の製造メーカーで、画材や文具なども販売されています。
画材店やオンラインショップでも取り扱いが多いため、手に入りやすいメーカーです。
私が初めて購入したのが、名村大成堂の彩色筆でした。
とても描きごごちが良く、私が日本画の筆を使ってみたいと思うきっかけになった筆です。
日本画の筆|筆のおろし方とお手入れ方法
筆は使っていくうちに、毛先が摩耗してしまう消耗品ではありますが、お気に入りの筆は、なるべく長く綺麗に保ちたいですよね。
そのためには、日ごろの取り扱いや、お手入れが大切になります。
<筆のおろし方(使い始め)>
穂先が糊で固められていますので、穂先を水、又はぬるま湯につけて、穂先の方から徐々に根元の方まで指の腹でやさしく揉みほぐしながらおろしてください。
<使用後のお手入れ方法>
穂先を下にして筆洗の水の中にいれたままにしていると、穂先が曲がってクセが付いたり、抜け毛の原因になったりしますので、注意しましょう。
使用後は、水、又はぬるま湯で丁寧にやさしく絵の具を落とし、タオルなどの布で水気を拭き取ります。
この時、タオルに絵の具が付かなくなるまでよく洗います。
洗ったあとは、穂先を下にして吊るし、よく乾かしてください。


<筆の保管>
よく乾燥させたのち、穂先を真っ直ぐにした状態で保管します。
購入した際、穂先に付いていたキャップはせずに保管しましょう。
(使用後にキャップをすると穂先が蒸れて筆が痛む原因になります。)





筆のお手入れの方法は下記の記事の中で詳しく解説していますので、あわせて読んでみてくださいね。


まとめ
職人さんの高い技術で作られた日本画の筆の描き心地に馴染むと、きっと手放せない筆になると思います。
水彩画にとって、水彩紙は出来具合を左右する重要な要素ですが、筆も絵の上達に影響する重要な道具であると言えます。
日本画の筆は、価格も比較的高いものが多く、初心者さんにとっては、少し敷居が高い筆かもしれませんが、適切なお手入れで描きやすい筆を長く使えば、コスト的にもお得と言えるかもしれません。
水彩画にも活躍すること間違い無しの日本画の筆を是非試してみてくださいね。
